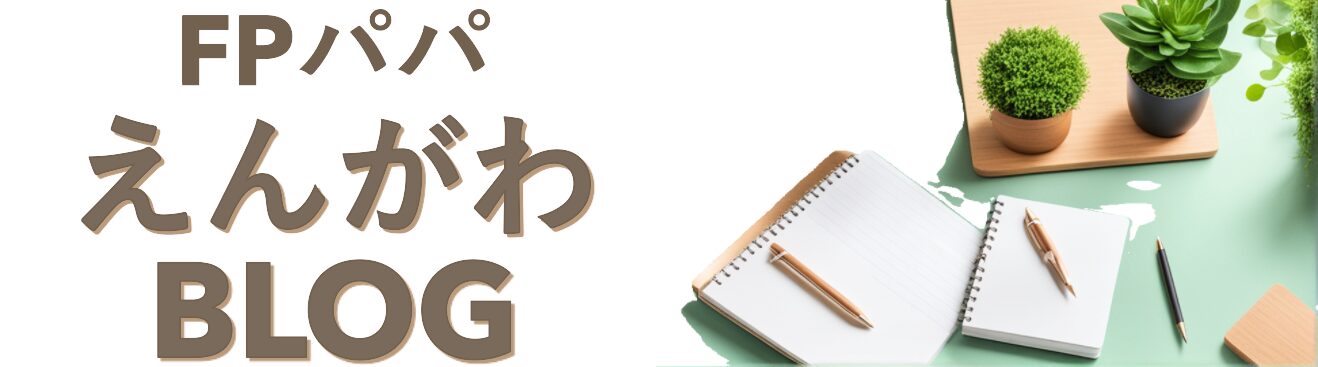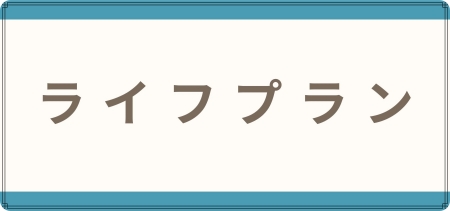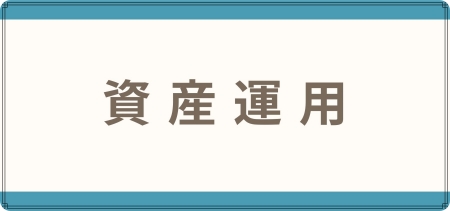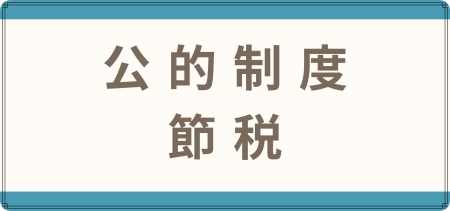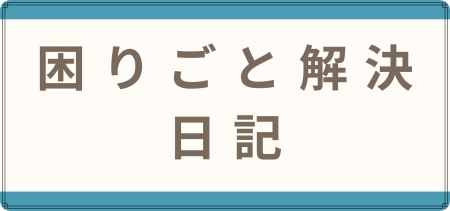いくら
いくらNISAとかiDeCoとか投資の節税制度がいくつかあるんだよね?
どれを使えばいいの?



人によって違うんだ。
NISA、iDeCo以外にも企業型確定拠出年金、小規模企業共済などもあるよ。
制度によっては損をしてしまうこともあるから、注意が必要だよ。
まずは各制度のメリット・デメリットをまとめたよ。
各制度の制度比較、メリット・デメリット比較
| 項目 | NISA | iDeCo | 企業型確定拠出年金 | 小規模企業共済 |
|---|---|---|---|---|
| 目的 | 資産運用 | 老後資金 | 老後資金 | 退職金 |
| 加入対象者 | 誰でも(18歳以上) | 20歳以上70歳未満 ※60~69歳は条件あり | 勤務先で制度がある従業員 | 自営業者・小規模法人の役員など |
| 掛金上限(月額、年額) | 年360万円 (つみたて投資枠:年120万円 成長投資:年240万円) | 自営業:月6.8万円 会社員:月2〜2.3万円 | 企業側で設定(例:月5.5万円など) 自己負担で増額可能(マッチング拠出) | 月7万円 |
| 掛金上限(合計) | 1,800万円 | 上限なし | 上限なし | 上限なし |
| 引き出し制限 | いつでも可能 | 60歳~75歳 | 60歳~75歳 | 廃業・退職等でのみ受け取り可能 |
| 運用商品 | 株式・投資信託など幅広く選べる | 投資信託・定期預金など金融機関ごとに選べる商品が異なる | 会社指定の商品から選択 | 運用は不要(共済金として受取) |
| 主なメリット | ・売却益、配当金が非課税 ・引き出し自由 ・投資枠が大きい(最大360万/年) | ・掛金が所得控除 ・運用益非課税 ・受取時に税優遇 | ・会社が拠出(自己負担なしも可) ・自己負担分は掛金が所得控除 ・運用益非課税 ・受取時に税優遇 | ・掛金が所得控除 ・元本保証 ・運用不要 ・受取時に税優遇 |
| 主なデメリット | ・所得控除なし ・損失時に他の利益と損益通算不可 | ・原則60歳まで引き出せない ・商品種類が少ない ・毎月手数料あり ・受取時に税金がかかる可能性 | ・勤務先に制度がないと利用不可 ・商品種類が少ない ・原則60歳まで引出不可 ・受取時に税金がかかる可能性 | ・廃業・退職などでないと原則引き出せない ・任意解約で元本割れの可能性 ・受取時に税金がかかる可能性 |
| 項目 | NISA | iDeCo |
|---|---|---|
| 目的 | 資産運用 | 老後資金 |
| 加入対象者 | 誰でも(18歳以上) | 20歳以上70歳未満 ※60~69歳は条件あり |
| 掛金上限(月額、年額) | 年360万円 (つみたて投資枠:年120万円 成長投資:年240万円) | 自営業:月6.8万円 会社員:月2〜2.3万円 |
| 掛金上限(合計) | 1,800万円 | 上限なし |
| 引き出し制限 | いつでも可能 | 60歳~75歳 |
| 運用商品 | 株式・投資信託など幅広く選べる | 投資信託・定期預金など金融機関ごとに選べる商品が異なる |
| 主なメリット | ・売却益、配当金が非課税 ・引き出し自由 ・投資枠が大きい(最大360万/年) | ・掛金が所得控除 ・運用益非課税 ・受取時に税優遇 |
| 主なデメリット | ・所得控除なし ・損失時に他の利益と損益通算不可 | ・原則60歳まで引き出せない ・商品種類が少ない ・毎月手数料あり ・受取時に税金がかかる可能性 |
| 項目 | 企業型確定拠出年金 | 小規模企業共済 |
|---|---|---|
| 目的 | 老後資金 | 退職金 |
| 加入対象者 | 勤務先で制度がある従業員 | 自営業者・小規模法人の役員など |
| 掛金上限(月額、年額) | 企業側で設定(例:月5.5万円など) 自己負担で増額可能(マッチング拠出) | 月7万円 |
| 掛金上限(合計) | 上限なし | 上限なし |
| 引き出し制限 | 60歳~75歳 | 廃業・退職等でのみ受け取り可能 |
| 運用商品 | 会社指定の商品から選択 | 運用は不要(共済金として受取) |
| 主なメリット | ・会社が拠出(自己負担なしも可) ・自己負担分は掛金が所得控除 ・運用益非課税 ・受取時に税優遇 | ・掛金が所得控除 ・元本保証 ・運用不要 ・受取時に税優遇 |
| 主なデメリット | ・勤務先に制度がないと利用不可 ・商品種類が少ない ・原則60歳まで引出不可 ・受取時に税金がかかる可能性 | ・廃業・退職などでないと原則引き出せない ・任意解約で元本割れの可能性 ・受取時に税金がかかる可能性 |
以下に税制メリットをまとめた比較表を記載します。
| 項目 | NISA | iDeCo | 企業型確定拠出年金 | 小規模企業共済 |
|---|---|---|---|---|
| 税制メリット①(掛金) | なし | 所得控除 | 所得控除 ※自己負担分のみ | 所得控除 |
| 税制メリット②(運用益) | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税(利子) |
| 税制メリット③(一括で受取) | 非課税(配当金、売却益) | 退職所得控除 | 退職所得控除 | 退職所得控除 |
| 税制メリット④(年金で受取) | 年金での受取不可 | 公的年金等控除 | 公的年金等控除 | 公的年金等控除 |



iDeCo、企業型確定拠出年金、小規模企業共済は似てるんだね。



老後に向けた準備という側面が強いからね。
NISAはお金が必要になった時にいつでも売れるから、そこが特に大きな違いなるかな。
制度を利用する時はよく考えることが重要だよ。



○○控除っていっぱい書いてあって、どれを使えばいいのかよくわからないよ。



実は最善案を計算するのは、すごく複雑なんだよね。。。
面倒くさいという人は、NISAだけでいいと思います。
※余計な税金を取られる心配がないため。
下記にタイプ別のオススメ投資方法をまとめてみたよ。
ちなみにですが、ケースによってはNISAよりiDeCoなどのほうが節税になることがありえます。
タイプ別のオススメ投資方法
いくつかのタイプに分類して、オススメの制度利用法を記載していきます。
iDeCo、企業型確定拠出年金、小規模企業共済について、退職所得控除を利用した節税効果が高いため、一括で受け取る方式を前提とします。
- 退職金がない方 or 少ない方(会社員など)
- 退職金が多い方(会社員、公務員など)
- 収入が少ない方(引退世代、専業主婦など)
- 小規模な事業者や個人事業主
退職所得控除の活用
ポイントになるのが、退職所得控除です。
【iDeCo】【企業型確定拠出年金】【小規模企業共済】は退職所得控除が利用できます。
退職所得控除とは勤続年数、加入年数に応じて税金を安くしようというものです。
退職所得控除の計算は以下です。
※勤続年数、加入年数は会社の勤続年数、iDeCoや企業型確定拠出年金の加入年数となり、長い方の年数になります。
- ▼20年以下(勤続年数または加入年数)
-
40万円 × 年数 = 退職所得控除
- ▼20年超(勤続年数または加入年数)
-
800万円 + 70万円 × (年数ー20年) = 退職所得控除
税金を計算するための退職所得の計算は以下になります。
(退職金+運用額 ー退職所得控除)÷2 = 退職所得
※運用額とは、iDeCoや企業型確定拠出年金の評価額になります。
例として、退職金1,500万円、iDeCo500万、勤続年数30年の場合は以下です。
- 退職所得控除
-
800万円 + 70万円×(30年ー20年)=1,500万円
- 退職所得
-
(1,500万円 + 500万円 ー 1500万円)÷2=250万円
250万円が退職所得となり、税金は40万円ほどです。
退職金の税金について詳しく知りたい方は、以下記事をご覧ください。


退職金がない方 or 少ない方(会社員)
以下の順で埋める
①「iDeCo」or「企業型確定拠出年金のマッチング拠出」(60歳まで使う予定のない額)
②「NISA」
退職金がない or 少ないという方はiDeCoまたは企業型確定拠出年金のマッチング拠出を優先して埋めたほうがよいです。
iDeCoは掛金が所得控除、受取時に退職所得控除が使えます。
分かりやすく言うと、「毎年の所得税・住民税を減らせる」、「受取時の税金をゼロ」にすることが可能です。
NISAと比較して毎年の所得税、住民税を減らせる分、節税効果が見込めます。
会社員で独身(扶養家族なし)とした場合の年収、減税額は以下です。
※扶養家族の有無、控除などによっても異なりますので、あくまで目安としてください。
| 年収 | 課税所得 | 節税となる率 ※住民税10%との合計 | 年間減税額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年6万購入 (月0.5万) | 年24万購入 (月2万) | 年74.4万購入 (月6.2万) | |||
| 480万以下 | 195万以下 | 15% ※所得税5% | 9,000円 | 36,000円 | 111,600円 |
| 480万~670万 | 195万~330万 | 20% ※所得税10% | 12,000円 | 48,000円 | 148,800円 |
| 670万~1,070万 | 330万~695万 | 30% ※所得税20% | 18,000円 | 72,000円 | 223,200円 |
| 1,070万~1,300万 | 695万~900万 | 33% ※所得税23% | 19,800円 | 79,200円 | 245,520円 |
| 1,300万~2,220万 | 900万~1,800万 | 43% ※所得税33% | 25,800円 | 103,200円 | 319,920円 |
| 年収 | 課税所得 | 節税となる率 ※住民税10%との合計 |
|---|---|---|
| 480万以下 | 195万以下 | 15% ※所得税5% |
| 480万~670万 | 195万~330万 | 20% ※所得税10% |
| 670万~1,070万 | 330万~695万 | 30% ※所得税20% |
| 1,070万~1,300万 | 695万~900万 | 33% ※所得税23% |
| 1,300万~2,220万 | 900万~1,800万 | 43% ※所得税33% |
| 年収 | 年間減税額 | ||
|---|---|---|---|
| 年6万購入 (月0.5万) | 年24万購入 (月2万) | 年74.4万購入 (月6.2万) | |
| 480万以下 | 9,000円 | 36,000円 | 111,600円 |
| 480万~670万 | 12,000円 | 48,000円 | 148,800円 |
| 670万~1,070万 | 18,000円 | 72,000円 | 223,200円 |
| 1,070万~1,300万 | 19,800円 | 79,200円 | 245,520円 |
| 1,300万~2,220万 | 25,800円 | 103,200円 | 319,920円 |
受取時の節税についてですが、退職所得控除が使えます。
将来受け取る退職金、退職所得控除額を確認しつつ、iDeCoの金額を検討してください。
以下の計算に収まっていれば、損する事はないです。
退職所得控除の金額 > 退職金 + iDeCo(評価額)
退職所得控除の金額
- ▼20年以下(勤続年数または加入年数)
-
40万円 × 年数 = 退職所得控除
- ▼20年超(勤続年数または加入年数)
-
800万円 + 70万円 × (年数 ー 20年) = 退職所得控除
※注意点として、iDeCoは積立額ではなく、受取時の評価額になりますので、毎年3~5%上がる想定して計算するとよいです。
退職金が多い方(会社員、公務員など)
以下の順で埋める
①「NISA」
②「iDeCo」 or 「企業型確定拠出年金のマッチング拠出」
退職金が多い方はNISAを優先して埋めたほうがよいです。
退職金が多い方は、控除額を超えてしまう可能性が高いため、iDeCoなどに金額を回せる金額が元々少なく、節税額が小さいため、NISAを優先しています。
※例えば勤続年数が38年の場合で、控除額は2,060万円です。(800万+70万×(38-20))
iDeCoや企業型確定拠出年金のマッチング拠出を利用したい場合は、退職金控除額内で利用するようにしましょう。
退職金控除額を超過してしまうと、一般的に証券口座で投資信託を購入した場合と比較して、損をしてしまう可能性が出てくるためです。
収入が少ない方(引退世代、専業主婦など)
「NISA」のみ利用する
収入が少ない方は「NISA」のみ利用してください。
iDeCoをオススメしないのはメリットである所得控除を活用できないためです。
小規模な事業者や個人事業主
以下の順で埋める
①「iDeCo」(60歳まで使う予定のない額)
②「NISA」
③「小規模企業共済」(60歳まで使う予定のない額)
小規模な事業者や個人事業主の方はiDeCoを優先して埋めたほうがよいです。
iDeCoは掛金が所得控除、受取時に退職所得控除が使えるためです。
小規模企業共済についてはiDeCoと同様の控除が使えるのですが、利率が低いため優先度としては最後にしています。
iDeCoや小規模企業共済の金額は、退職金控除額内で利用するようにしましょう。
退職金控除額を超過してしまうと、証券口座で投資信託を持っていた場合と比較して損をしてしまう可能性が出てきます。
各制度の説明



下記に各制度の詳細説明を記載したよ。
改めて確認したい人は見てみて!
NISA(少額投資非課税制度)
節税
通常、株式や投資信託の運用益(配当・譲渡益など)には20.315%の税金がかかります。
NISA口座の投資で得た運用益は、この税金がかかりません。
手数料
なし
購入できる銘柄
「つみたて投資枠」で購入できる銘柄(投資信託)は、金融庁が定めた基準を満たす長期・積立・分散投資に適した商品に限定されています。
また、証券会社によって銘柄が異なります。
「金融庁がOKしたもの」の中から、各社が「取り扱い商品」として選んでいるためです。
「成長投資枠」で購入できる銘柄は、上場株式(個別株)、投資信託、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)に限定されています。
※すべて国内で上場している銘柄のみです。米国のETFなどは対象外です。
また、つみたて投資枠と同様、証券会社によって銘柄が異なります。
つみたて投資枠と同じ銘柄も購入が可能です。
掛金上限
利用できる額は年間でつみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円が最大です。
合計で1,800万円まで利用可能です。
また、つみたて投資枠だけで1,800万円埋めることも可能ですが、成長投資枠は1,200万円までです。
売却タイミング
購入した株式や投資信託はいつでも売却可能です。
また、NISA口座は1,800万円の使い切りではありません。
保持していた銘柄を売却した場合、翌年1月1日に売却した額が、そのまま投資枠として復活します。
ただし、年間で購入できる額は360万円が上限であることには変わりありません。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
※60歳~70歳未満の方は条件があり、会社員や公務員として働き、厚生年金保険の被保険者である場合、または国民年金に任意加入している場合に加入できます。
節税
掛け金が所得控除になります。
つまり、給与収入などの所得税、住民税が節税になります。
一括で受け取る場合に退職所得控除、年金方式で受け取る場合に公的年金等控除が利用できます。
どちらの場合でも控除額をオーバーすると、税金がかかります。
手数料
加入時:2,829円(初回のみ)
毎月:171円(最低額)※証券会社によって異なる
受取時:440円
購入できる銘柄
投資信託、定期預金(元本保証)、年金保険などの保険商品(元本保証)があります。
証券会社によって銘柄が異なりますが、NISAと比較して選択できる銘柄は非常に少ないです。
掛金上限 ※現行
| 加入者の区分 | 掛け金上限(月額) | 掛け金上限(年額) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自営業・フリーランス(第1号被保険者) | 68,000円 | 816,000円 | 国民年金基金と合わせた上限 |
| 会社員(企業年金なし) (第2号被保険者) | 23,000円 | 276,000円 | |
| 会社員(企業年金あり) (第2号被保険者) | 20,000円 | 240,000円 | |
| 専業主婦(夫)など (第3号被保険者) | 23,000円 | 276,000円 | 配偶者が厚生年金に加入していることが条件 |
| 公務員(共済年金などに加入) | 20,000円 | 240,000円 |
掛金上限 ※2025年度の税制改正後
| 加入者の区分 | 掛け金上限(月額) | 掛け金上限(年額) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自営業・フリーランス(第1号被保険者) | 75,000円 | 900,000円 | 国民年金基金の掛金と合計した上限 |
| 会社員(企業年金なし) (第2号被保険者) | 62,000円 | 744,000円 | |
| 会社員(企業年金あり) (第2号被保険者) | 62,000円 | 744,000円 | 企業年金の掛金と合計した上限 |
| 専業主婦(夫)など (第3号被保険者) | 23,000円 | 276,000円 | 配偶者が厚生年金に加入していることが条件 |
| 公務員(共済年金などに加入) | 62,000円 | 744,000円 |
売却タイミング
原則60歳以降にならないと売却できないです。60~75歳の間に売却しなければいけません。
iDeCoは手数料がかかるからNISAのほうがいい?
iDeCoは手数料が高いからNISAのほうがよいという方がいますが、誤りです。
iDeCoのランニングの手数料は毎月171円(大手ネット証券)です。
毎月5,000円積立で、171円だと手数料が3%とられるじゃないかという理屈です。
毎月発生する手数料は、保持している銘柄がいくらであろうと毎月171円(年間2,052円)です。
1年目は手数料の割合が高いですが、年数を追うごとに下がります。
10年も購入すれば、全世界株式(オール・カントリー)などの手数料が安い投資信託と大差ありません。
▼毎月5,000円、年間60,000円を購入した場合
1年目:積立額60,000円、年間手数料2,052円、手数料の割合3.42%
2年目:積立額120,000円、年間手数料2,052円、手数料の割合1.71%
5年目:積立額300,000円、年間手数料2,052円、手数料の割合0.684%
10年目:積立額600,000円、年間手数料2,052円、手数料の割合0.342%
企業型確定拠出年金
会社負担で退職金・年金を積み立てする制度です。
節税
iDeCoと同様で、掛け金が所得控除になります。
一括で受け取る場合に退職所得控除、年金方式で受け取る場合に公的年金等控除が利用できます。
1点だけ補足として、企業型確定拠出年金は、自己負担分の掛け金のみ(マッチング拠出)が所得控除になります。
企業側の拠出分は所得控除になりません。
手数料
受取時:440円
※毎月の手数料は一般的には企業負担ですが、個人負担となることもあります。
購入できる銘柄
会社指定の商品から選択します。
主に元本保証型商品(定期預金、年金保険など)、投資信託になります。
NISAと比較して選択できる銘柄は非常に少ないです。
掛金上限
企業側で設定します。
また、自身の負担で積立額を増やすこと(マッチング拠出)ができます。
売却タイミング
原則60歳以降にならないと売却できないです。60~75歳の間に売却しなければいけません。
また、退職後に引き続き運用したい場合は、iDeCoに移管することが可能です。
小規模企業共済
個人事業主や小規模企業の経営者のための退職金制度です。
節税
iDeCoと同様で掛け金が所得控除になります。
一括で受け取る場合に退職所得控除、年金方式で受け取る場合に公的年金等控除が利用できます。
手数料
なし
購入できる銘柄
退職金積立制度であるため、特定の銘柄を購入するわけではありません。
利率は年率1%程度です。
掛金上限
1,000円〜70,000円までの範囲で、500円単位で自由に設定可能です。
iDeCoと併用が可能です。(小規模企業共済とiDeCoのそれぞれの上限まで購入可能です。)
売却タイミング
廃業・退職した時に受け取りになります。