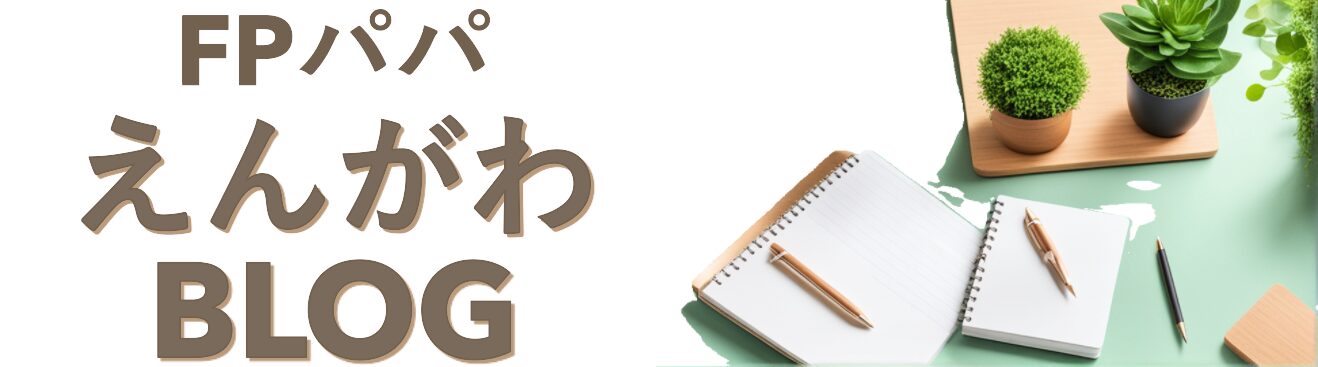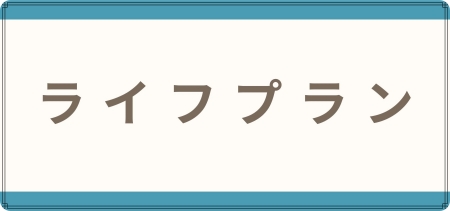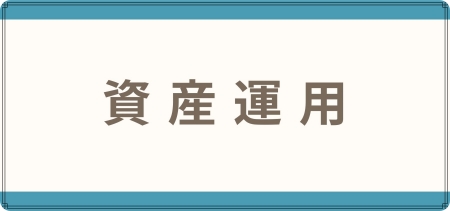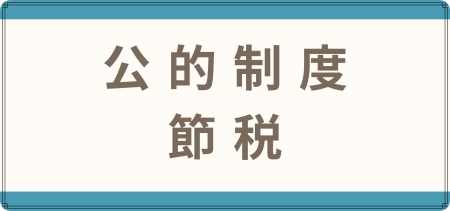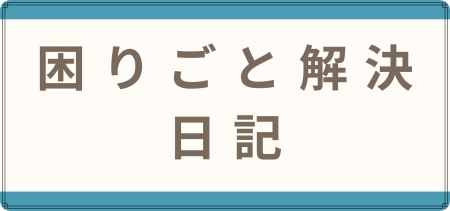【節税方法について学ぼう】
代表的な節税方法の種類
代表的な節税の方法について説明していきます。
 いくら
いくら今度は節税だね。
どういう種類があるの?



「投資」「住宅」「保険」「ふるさと納税」「退職金」などになるよ。
具体的にどういう時に使えるか代表的な制度を説明していくよ。
1点だけ注意があるよ。
制度を利用するためには何もしなくてももらえるわけではなくて、自分で申請が必要なものが大半だよ。



取られるときは強制なのに。
ズルいよ。



こればっかりは仕方ないね。
手間だけど金額が大きいから必ず制度を利用したほうがいいよ。
もっと詳しく知りたいっていう人はFP3級の資格取得をおすすめするよ。



仕事が忙しくて勉強する時間なんてないよ。。



受験者の合格率は80%は超えているし、1か月くらい勉強すれば合格できるよ。
本音を言うと、義務教育で教えてほしいレベルなんだ!
以下におすすめの本を記載するので気になる方はぜひ、勉強してみて。
何かあった時に制度があることを知っておくことで、損をしないようにしよう!
所得控除、税額控除について
節税の種類の前に、「所得控除」と「税額控除」の違いについてです。
制度によって、控除される対象が異なるため、初めに説明を記載しておきます。
税金の計算過程を理解する必要があるため、以下に記載します。
① 年収(給与など)
↓
② 所得(年収 - 必要経費など)
↓
③ 課税所得(所得 - 所得控除)
↓
④ 税金(課税所得 × 税率)
税金を計算する時には、収入から経費や所得控除が引かれた「課税所得」をまずは出します。
課税所得に対して税率をかけて、所得税、住民税が決定されます。
所得控除
所得控除は、控除の金額がそのまま節税される金額になるわけではありません。
所得控除は上記計算③で記載したように、課税所得を出すときに引き算されるものです。
④で税率を掛けますので、実際の節税額はそれほど多くありません。
例として、年収800万円の会社員の場合で計算してみます。
所得税率20%、住民税10%、生命保険料を年間4万円支払(所得控除4万円)。
節税額の計算式は以下です。
所得税:4万円×20%=0.8万円、住民税:4万円×10%=0.4万円
合計:1.2万円(0.8万円+0.4万円)
このケースの場合、所得控除4万円に対して、節税額は1.2万円となります。
税額控除
税額控除は、税金をそのまま引きます。
上記計算の④の税金からそのまま引きます。
そのため、所得控除と異なり、控除金額がそのまま節税になります。
例として、住宅ローン減税で税額控除が28万円であれば、そのまま所得税が28万円節税になります。
節税(投資)
投資をしたい
NISA(少額投資非課税制度)
通常、株式や投資信託の運用益(配当・譲渡益など)には20.315%の税金がかかります。
NISA口座の投資で得た運用益は、この税金がかかりません。
利用できる額は1年間でつみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円が最大です。
合計で1,800万円まで利用可能です。
購入した株式や投資信託はいつでも売却可能です。
口座開設年の1月1日時点で18歳以上であることが条件です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
※60歳~70歳未満の方は条件があり、会社員や公務員として働き、厚生年金保険の被保険者である場合、または国民年金に任意加入している場合に加入できます。
会社員だが退職金がない or 少ない、自営業のため退職金がない場合などに有効な節税方法です。
通常、株式や投資信託の運用益(配当・譲渡益など)には20.315%の税金がかかります。
iDeCoもNISA同様にこの税金がかかりません。
NISAと異なり掛金に応じて、税金(所得税、住民税)を減らすことができます。(所得控除)
利用できる額は人によって異なり、20,000円~68,000円の幅になります。※2025年時点
受け取り時に退職所得控除が使えますが、受け取り時に税金がかかる場合がありますので、利用するかどうかは検討が必要です。
他にもNISAと異なる点がいくつかありますので、下記の企業型確定拠出年金、小規模企業共済と合わせて別記事で解説します。
企業型確定拠出年金
会社負担で退職金・年金を積み立てする制度です。
企業が本制度を利用していない場合は使えません。
会社員だが退職金が少ない場合などに有効な節税方法です。
自身の負担で積立額を増やすこと(マッチング拠出)ができ、自身負担分は税金を減らすことができます。(所得控除)
ただし、マッチング拠出をするとiDeCoは使えなくなります。
iDeCoと同様に受け取り時に退職所得控除が使えますが、受け取り時に税金がかかる場合がありますので、利用するかどうかは検討が必要です。
小規模企業共済
個人事業主や小規模企業の経営者のための退職金制度です。
掛け金に応じて、税金を減らすことができます。(所得控除)
自営業のため退職金がない場合などに有効な節税方法です。
iDeCoと同様に受け取り時に退職所得控除が使えますが、受け取り時に税金がかかる場合がありますので、利用するかどうかは検討が必要です。
どの制度を利用した方がいいか、詳しく知りたい方向けに以下記事にてまとめています。


投資で損をした
損益通算
通常、株式や投資信託の運用益(配当・譲渡益など)には20.315%の税金がかかります。
株の売買で利益と損失が出た場合、損失分の税金を減らす制度です。
1/1~12/31の間の「利益」-「損失」=プラスになる金額が課税対象となります。
利益には配当金も含まれます。
基本的には確定申告が必要ですが、以下の条件であれば申告不要です。
口座:「特定口座」、「源泉徴収あり」かつ「配当受入あり」
配当金の受け取り方式:「株式数比例配分方式」
※証券会社の設定画面などで確認できます。
繰越控除
株式の売買などで損失が出て、損益通算をしても損失が残る場合は、翌年以降3年まで損失を繰越できる制度です。
1/1~12/31の間の「利益」ー「損失」=マイナスになる場合です。
翌年以降に利益が出た場合、マイナス分が損益通算でき、税金を減らせます。
3年間損失を繰り越すためには、3年の間、取引が行われていない年でも確定申告が必要です。
配当金をもらった
配当控除
※上場不動産投資信託(J-REIT)には使用できません。
通常、株式や投資信託の配当金には20.315%の税金がかかります。
配当控除は配当金の税金を減らす制度(5%または10%)です。
※減らせる税率は所得によって異なります。
制度を利用するためには確定申告が必要です。
配当控除を利用する場合、総合課税で税金を支払う必要があります。
総合課税とは他の収入(給与収入など)と配当収入を合算して、税金を払うという意味です。
結果的に損する可能性がありますので注意が必要です。
どんな場合に得をするのかは下記の外国税額控除と合わせて別記事で解説します。
外国株の売買で利益が出た、配当金をもらった
外国税額控除
外国株の売買の利益、配当金について、外国に支払った税金を取り戻す制度です。
外国で税金が引かれた後に、日本で税金を引かれてしまうので2重課税となっているため、本制度があります。
国によって異なりますが、米国だと10%税金がかかっています。
制度を利用するためには確定申告が必要です。
また、外国税額控除は外国で支払った税金が、必ず全て戻ってくるわけではありません。
細かい計算がありますので別記事にて解説します。
節税(定期的に発生)
住宅をローンで購入した
住宅ローン控除
10~13年の間、住宅ローンの年末残高に応じて、税金を減らすことができます。(税額控除)
新築住宅の場合、年末時点での借入残高が3,000万~5,000万円が上限になります。
中古住宅の場合、年末時点での借入残高が2,000万~3,000万円が上限になります。
年数や金額は、「住宅の種類」、「子育て世帯・若者世代かどうか」によって異なります。
控除率は0.7%です。
例として、借入残高の上限が4,000万円で、年末時点で5,000万円借入残高がある場合、
借入残高が上限を超えていますので、上限の4,000万円で計算します。
4,000万円×0.7%=28万
税額控除ですので、28万以上の所得税を納めている場合、この年は28万円が戻ってきます。
※所得税で引ききれない場合は、翌年度の住民税が控除されます。
会社員、公務員の方は1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で提出が可能です。
※年数、金額、控除率は2025年で借入する場合です。
民間保険を契約している
「生命保険料控除」「地震保険料控除」
対象の保険については、支払った各保険料に応じて、税金を減らすことができます。(所得控除)
以下に記載している金額は年間の保険料掛け金です。
生命保険料控除は「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3つにわかれています。
所得税は40,000円、住民税は28,000円が上限で、3つ別々に利用可能です。
3つ合計での上限は、所得控除は120,000円、住民税は70,000円です。
※2012年以降の契約の場合です。
地震保険料控除の上限は所得税50,000円、住民税25,000円です。
会社員、公務員の方は年末調整で提出が可能です。
自治体に寄付をした
ふるさと納税
寄付した金額から2,000円を除いた額の分、税金を減らすことができます。(所得税は所得控除、住民税は税額控除)
つまり2,000円で自治体からお礼の品が貰えるということになります。
納める予定の税金の一定額までしか控除されません。
寄付できる上限金額はシュミレーションサイト(ふるさとチョイスなど)で確認してください。
5つまでの自治体への寄付であれば、ワンストップ特例を使うことで確定申告は不要になります。
6つ以上の自治体に寄付をしてしまった場合は、確定申告が必要です。
※ワンストップ特例は住民税から税額控除、確定申告は所得税が所得控除、住民税から税額控除されます。
節税(一時的に発生)
高額な医療費を払った
医療費控除
1年間(1/1~12/31)で支払った医療費が10万円を超えた場合、超えた分について税金を減らすことができます。(所得控除)
本人だけでなく、生計を一つにする配偶者、親族の分も支払っていれば含めて適用可能です。
控除額の上限は200万です。
※総所得金額が200万未満の場合は、総所得金額×5%が上限です。
制度を利用するためには確定申告が必要です。
退職金、iDeCo、企業型確定拠出年金、小規模企業共済を一時金で受け取った
退職所得控除
退職金などの一時金に対して、税金を減らす制度になります。
また、退職金は分離課税ですので、他の所得(給与など)とは別に税金が計算されます。
退職金という名前がついていますが、【iDeCo】【企業型確定拠出年金】【小規模企業共済】にも利用ができます。
基本的な退職所得の計算は以下です。
- 20年以下(勤続年数または加入年数)
-
(退職金または運用額 ー(40万円×年数))÷2 = 退職所得
- 20年超(勤続年数または加入年数)
-
(退職金または運用額 ー(800万円 + 70万円×(年数ー20年)))÷2 = 退職所得
例として、退職金2,000万円、勤続年数30年の場合は以下です。
(2,000万円ー(800万円+70万円×(30年ー20年)))÷2=250万円
250万円が退職所得となり、おおよそ税金は40万円ほどです。
5年以下の勤続年数で、「役員の方」「役員以外でも高額な退職金を受け取る方」は計算方式が上記と異なりますが、ここでは割愛します。
【退職金】【iDeCo】【企業型確定拠出年金】【小規模企業共済】の併用については、注意が必要な点がありますので、詳細は別記事で説明します。



代表的な節税について記載したよ。
他にもいろいろな制度があるよ。
興味がある方はぜひFP3級の資格取得に挑戦してみて!