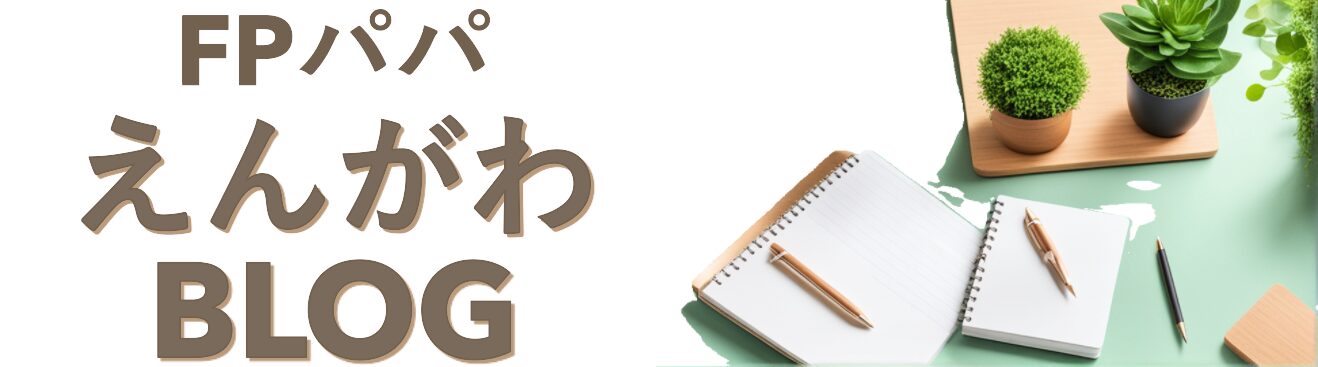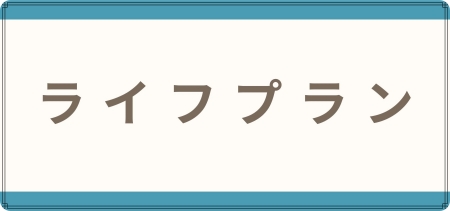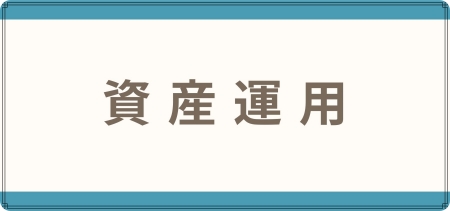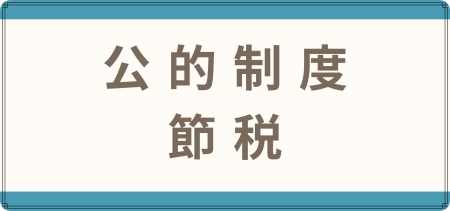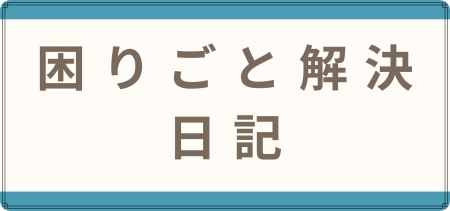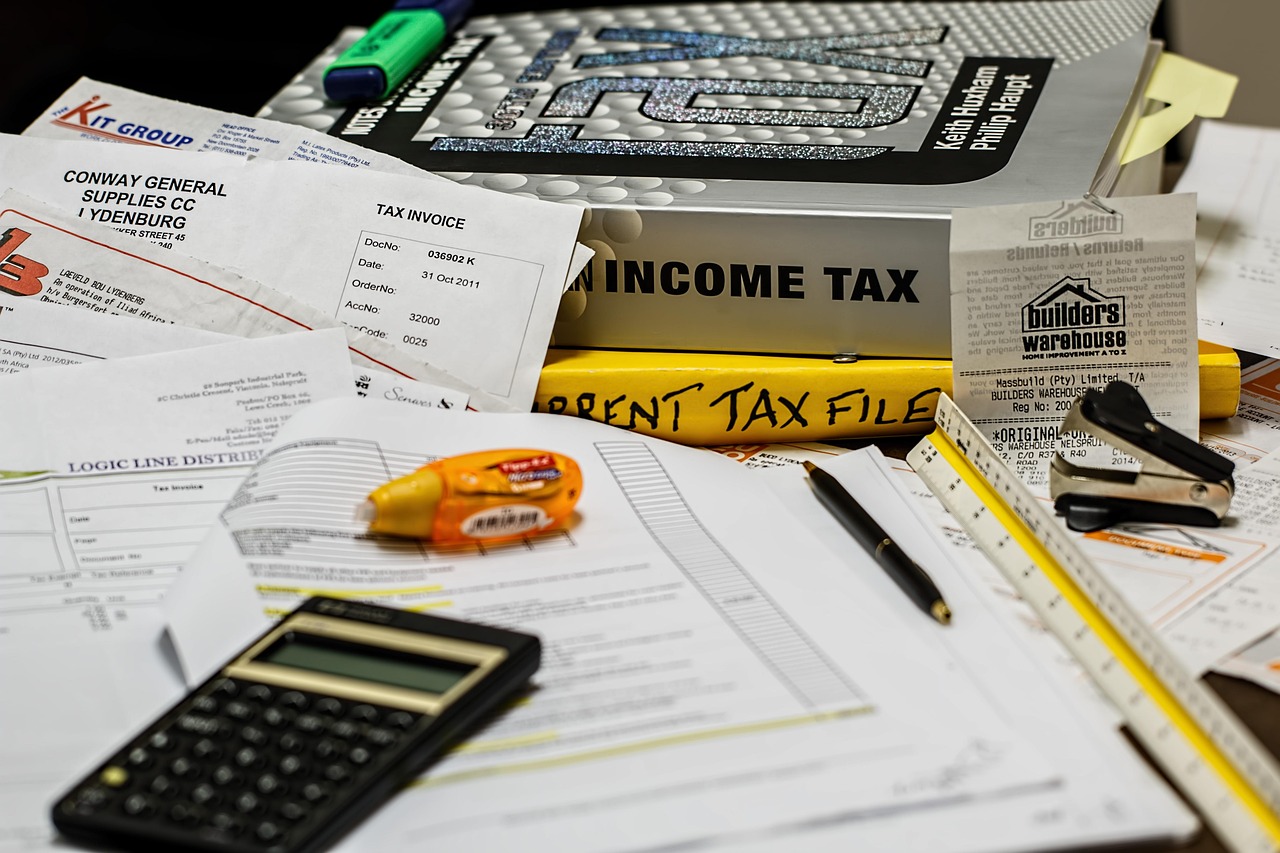【公的制度について学ぼう】
代表的な公的制度の種類
代表的な公的制度について説明していきます。
 いくら
いくら公的制度ってどういう種類があるの?



「年金」「失業」「出産・子育て」「医療費」「介護」「遺族年金」などを説明していくよ。



よく聞くワードが多いけど、どういう時に使えるの?



具体的にどういう時に使えるか代表的な制度を説明していくよ。
1点だけ注意があるよ。
給付金がもらえたり、医療費が減額される制度は何もしなくてももらえるわけではなくて、自分で申請が必要なものが大半だよ。



取られるときは強制なのに。
ズルいよ。



こればっかりは仕方ないね。
手間だけど金額が大きいから必ず制度を利用したほうがいいよ。
もっと詳しく知りたいっていう人はFP3級の資格取得をおすすめするよ。



仕事が忙しくて勉強する時間なんてないよ。。



受験者の合格率は80%は超えているし、1か月くらい勉強すれば合格できるよ。
本音を言うと、義務教育で教えてほしいレベルなんだ!
以下におすすめの本を記載するので気になる方はぜひ、勉強してみて。
何かあった時に制度があることを知っておくことで、損をしないようにしよう!
公的制度(子供)
子供が産まれた
出産育児一時金 ※国民健康保険、健康保険
出産後に1児につき50万円がもらえます。(2025年時点)
※夫、妻の加入しているどちらか一方の保険からもらえます。
出産手当金 ※健康保険
おおよそ出産前の給与の67%がもらえます。
出産日の42日前(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてもらえます。
※出産日が予定日より後になった場合は、出産予定日を基準とします。
育休手当(育児休業給付金) ※雇用保険
育休前の給与をベースとして、育休開始から28日までが80%、180日までが67%、181日目以降は50%がもらえます。
※80%については産後8週間以内に夫婦で14日以上の育児休業を取得することが条件です。
※金額には上限、下限があります。
夫:出産日または出産予定日の早い方の日付から育児休業可能
妻:出産後57日目以降から育児休業可能 ※56日までは上記の出産手当金
基本的には1歳まで取得可能ですが、1歳になっても保育所に入れないなどの特別な理由がある場合は、最長2歳まで延長が可能です。
公務員の場合は後述する「育児休業手当金」という別の制度になりますが、内容は同じです。
育児時短就業給付 ※雇用保険
子供が2歳未満で時短勤務(会社が定める週の労働時間よりも短時間勤務)で働いた場合、時短就業中の賃金のおおよそ10%がもらえます。
※時短勤務で給与が70%になった場合、7%分(70×10%)がもらえて総額が77%になります。
公務員の場合は後述する「育児時短勤務手当金」という別の制度になりますが、内容は同じです。
育児休業手当金、育児時短勤務手当金 ※公務員共済組合
内容は上記の「育休手当(育児休業給付金)」「育児時短就業給付」と同様です。
児童手当
条件として、日本国内に住所があれば支給されます。
3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上 18歳の誕生日後の初めの3月31日まで:10,000円(第3子以降は30,000円)
住んでいる地域によっては、自治体からも給付金がもらえる場合がありますので確認しましょう。
不妊治療で子供が欲しい
不妊治療
人工授精、体外受精などの保険適用が可能です。
治療開始時点の女性の年齢が40歳未満の場合は6回まで、43歳未満の場合は3回までと条件があります。
※回数は1子ごとにリセットされます。
住んでいる地域によっては、自治体から助成金がある場合がありますので確認しましょう。
公的制度(病気、失業)
医療費が高額になった
高額療養費制度 ※国民健康保険、健康保険
1か月(月初~月末)の医療費が高額となった場合に、決められた上限の支払額で済む制度です。
上限の支払額は収入に応じて変わります。
病気やケガで会社を休んだ、会社を退職し失業している
傷病手当金 ※健康保険
病気やケガで会社を3日連続して休んだ場合に、4日目以降に仕事に就けなかった場合が該当します。
4日目以降の会社を休んだ期間に対して、おおよそ給与の67%がもらえます。
連続する3日の休みは有給休暇でもかまいませんが、仕事に就けなかった4日目以降は無給であることが条件です。
求職者給付(基本手当)※雇用保険
一般的に失業保険と言われている制度です。
会社を退職後に、失業をしている場合に給付金がもらえます。
もらえる金額・期間は、直近の給与額・雇用保険の加入期間によって異なります。
条件として、自己都合退職は過去2年間に12ヵ月、倒産・解雇は過去1年間に6ヵ月の雇用保険加入が必要です。
※公務員は雇用保険に加入できないため、対象外です。
病気で介護が必要になった
介護保険
40歳以上の場合に利用可能な制度ですが、40歳以上65歳未満は特定疾病(認知症、末期がんなど)の場合のみ利用可能です。
要介護と認定された場合、在宅サービス(自宅で受けられる介護)、施設サービス(入所型)などが1割負担で利用できます。
要支援と認定された場合、介護予防サービス(訪問介護、リハビリ)などが1割負担で利用できます。
また、1割負担でも負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度があります。
公的制度(年金)
高齢者になった(60~75歳)
公的年金についてになります。
2か月に1回、偶数月の原則15日に年金がもらえます。
2025年時点では受給開始年齢は65歳が基本になりますが、60歳~75歳の間で選択(繰り上げ受給・繰り下げ受給)することが可能です。
国民年金
受給には国民年金保険料を10年以上納付が必要です。
受給額は賃金や物価の変動に応じて毎年4月に改定されます。
※参考.2025年度は満額で年831,700円(月額69,308円)
20歳~60歳まで保険料を納付する必要があります。
納付期間が短いと受給額が減ります。
※対象者によっては保険料の納付が不要になるケース(第3号被保険者)、納付が猶予されるケース(学生)などがあります。
付加年金
任意加入で、国民年金を上乗せできる制度です。
受給額は200円×納付期間(月)が国民年金に加算されます。
支払額は月額400円を上乗せして支払ことができます。
つまり年金を2年以上受け取るのであれば、プラスになります。
厚生年金保険
受給には厚生年金保険料を1ヵ月以上納付が必要です。
また、厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれています。
受給額は在職時の年収(支払額)、納付期間によって異なります。
※参考までに2024年度の平均は約145,000円です。(国民年金+厚生年金)
厚生年金の加入要件を満たす方は16歳~70歳まで保険料を支払う必要があります。
障がい者になった
障がい者になってしまった場合に、年金がもらえる制度です。
年金とありますが、65歳未満でも利用可能です。
障害基礎年金
病気や事故などで障害者になってしまった場合に、年金がもらえる制度です。
障害等級1級、2級に該当する必要があります。
受給額は賃金や物価の変動に応じて毎年4月に改定されます。
※2025年度の参考
1級で年1,039,625円(月額86,635円)
2級で年831,700円(月額69,308円)
上記に加えて、子供の人数によって加算があります
受給条件はややこしいので別記事にて説明します。
障害厚生年金
病気や事故などで障害者になってしまった場合に、年金がもらえる制度です。
障害等級1級、2級、3級に該当する必要があります。
受給額は厚生年金の支払額に応じて異なります。
障害基礎年金と併給が可能です。
受給条件はややこしいので別記事にて説明します。
生計を維持されていた方が亡くなった
生計を維持されていた方が亡くなった場合に年金、一時金がもらえる制度です。
年金とありますが、65歳未満の方でも利用可能です。
遺族基礎年金
注意点として子供がいないともらえません。
子供の定義は年齢条件があり、18歳の誕生日後の初めの3月31日まで、または20歳未満で障害等級1,2級となります。
受給額は賃金や物価の変動に応じて毎年4月に改定されます。
※2025年度の参考
年831,700円(月額69,307円) ※昭和31年4月2日以後生まれ
年829,300円(月額69,108円) ※昭和31年4月1日以前生まれ
上記に加えて、子供の人数によって加算があります
受給条件はややこしいので別記事にて説明します。
また、国民年金の独自給付として「寡婦年金」「死亡一時金」という制度があるのですが、こちらも併せて別記事にて説明します。
遺族厚生年金
亡くなった人に生計を維持されていた①配偶者、子、②父母、③孫、④祖父母の方に年金がもらえる制度です。
全ての方にもらえるわけではなく、①~④の優先順になります。
受給額は厚生年金の支払額に応じて異なります。
遺族基礎年金と併給が可能です。
受給条件はややこしいので別記事にて説明します。
また、厚生年金の独自給付として「中高齢寡婦加算」「経過的寡婦加算」という制度があるのですが、こちらも併せて別記事にて説明します。



代表的な公的制度について記載したよ。
他にもいろいろな制度があるよ。
興味がある方はぜひFP3級の資格取得に挑戦してみて!