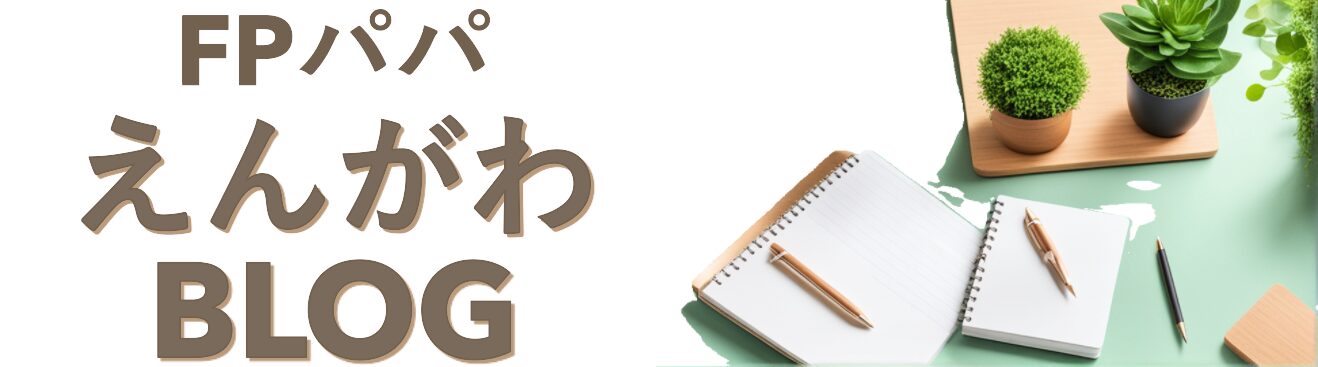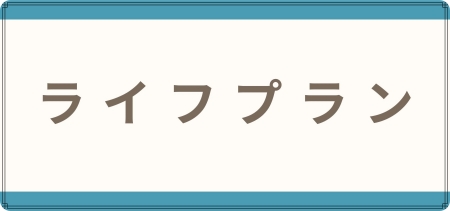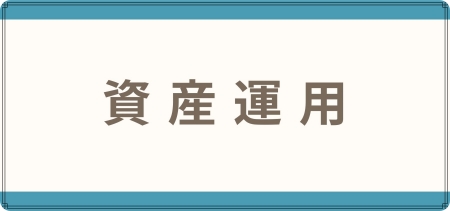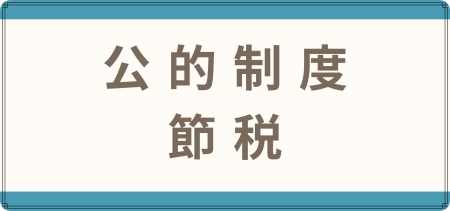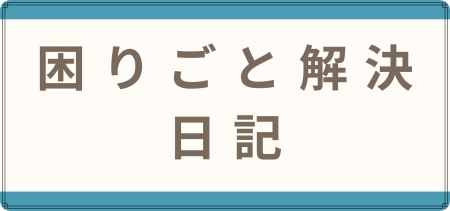【今から始める人生設計】
「家族のいる人生」「ひとりの人生」に備えよう
はじめまして。FP2級技能士のえんがわといいます。
本業は会社員(システムエンジニア)、妻・子供2人の4人家族です。
主に自分でライフプランを作成する方法、資産運用、公的制度/税金・節税について発信するブログとなります。
「皆さんはどのタイミングで将来のお金について考えることが多いでしょうか。」
私は人生の大きなライフイベントの転機に将来のお金について考える(心配になる)のではないかと思っています。
特に私の身近で発生している主に2つの世代に絞って解説ができればと考えています。
- 20代~40代の子育て世代
- 50代~60代の定年間近の独身世代
 まぐろ
まぐろなんでこの2つの世代に絞ったの?



子育て世帯は「家の購入」「子供の学費」などで将来お金が足りるか心配になることが多いんだ。
20代~40代の子育て世帯の友人からは、ライフプランや資産運用についての相談があって、自分達で調べて試行錯誤している人が多い印象なんだ。



独身世代はなんで50代~60代なの?



30代~40代の独身の友人からライフプランの相談はほとんどないんだ。
「NISAってやったほうがいいの?」という相談くらいかな。
現時点では将来の心配をしていなくて、とりあえず皆やっているから投資してみようかなっていう人が多いのかなと思ってる。
※私は将来心配しているよという方へ
「申し訳ございません。。。」



それより定年間近の独身の方から、老後が心配っていう話を聞くことが多かったんだ。
これは定年っていう大きなライフイベントがあるからなんだと思う。
そのため老後が気になってくる定年間近の50代~60代を対象にしているよ。



なるほど。
対象外の人はまだ見なくてもいいってこと?



もちろん。そんなことはないよ。
本音を言うと早いうちに備えておいてほしいんだ!
「年齢が少しずれている方」「資産運用について知りたい方」なども見ていただけますと幸いです!
ライフプラン作成、支出・収入の見直し
自分でライフプランを作成
ライフプランを作成して将来の資産状況を把握しましょう。
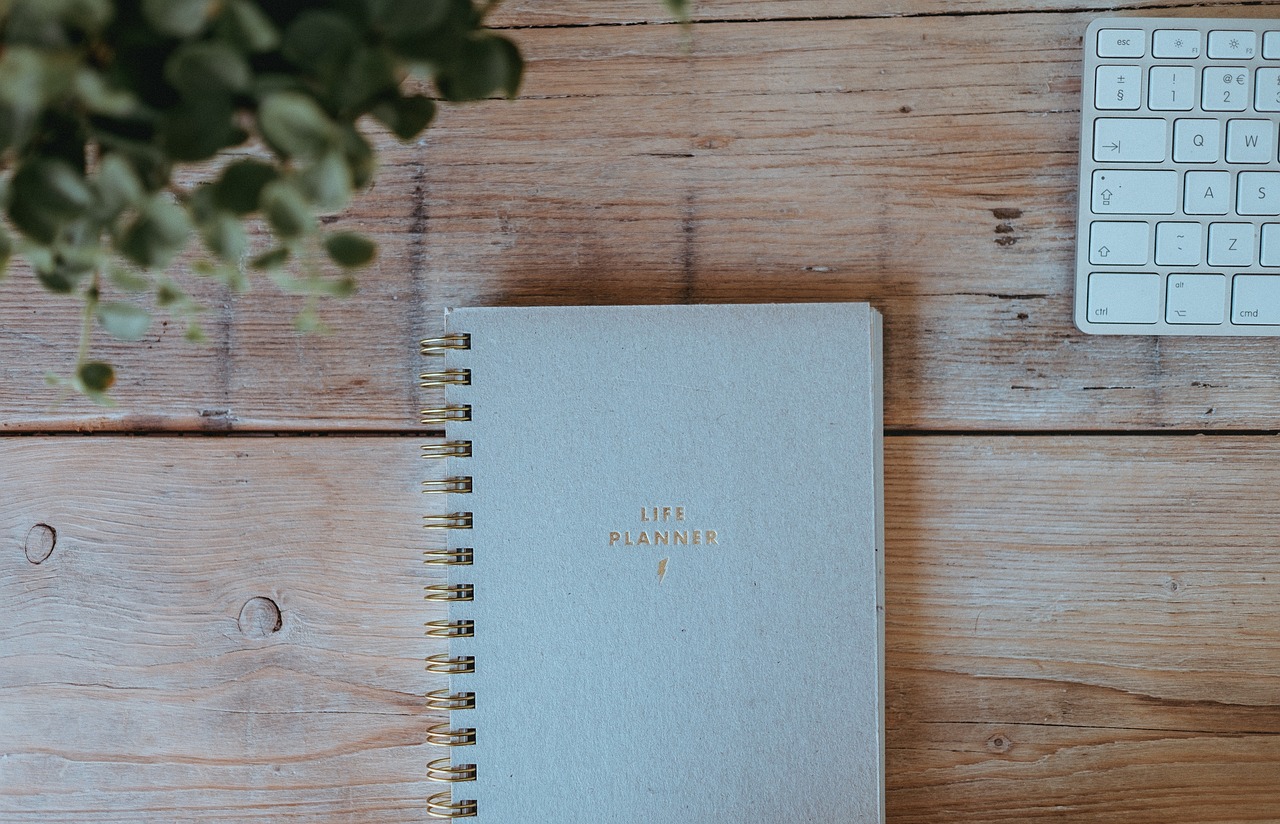
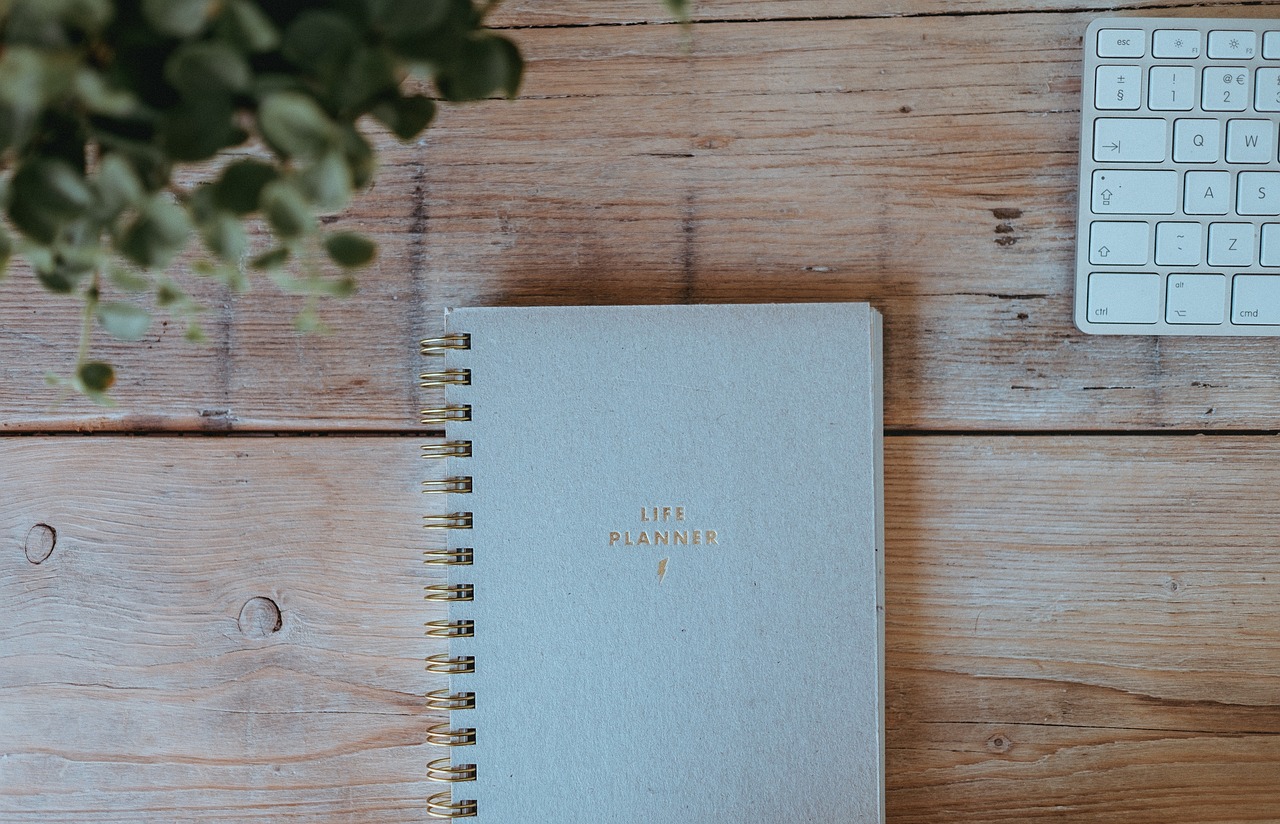
支出を減らす、収入を増やす
ライフプランを作成した結果が赤字になる、もう少し資金に余裕を持たせたい方は、「支出を減らす」「収入を増やす」などの対策をとりましょう。





ライフプランの作成とか面倒くさいよ。



本気で将来が心配ならできるはず!
【どうしても時間がない方】【資産運用について知りたい方】
次のステップの資産運用を始めてもかまいません。
資産運用
長期投資、投資金額の検討
長期投資について少し勉強しつつ、投資金額について検討しましょう。


投資先について
投資金額が決まったところで続いて具体的な投資先についてになります。




本ブログの記事一覧
本サイトは「ライフプラン」、「資産運用」、「公的制度・節税」、「悩み事解決・えんがわ日記」に記事をわけています。